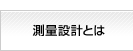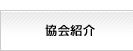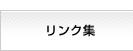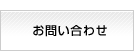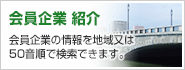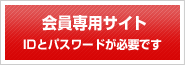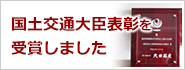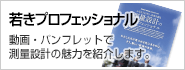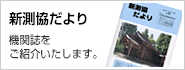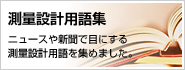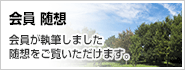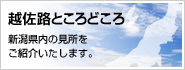6月3日は「測量の日」です。
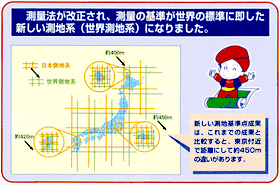
ひとりでも多くの人が地図に親しみ、測量の重要性について理解していただけたら、そんな願いをこめて始まった「測量の日」も今年で16年目を迎えました。
「測量の日」を中心に今年もいろいろなイベントを企画しています。
いままでの経験をいかし、皆様によりいっそう測量・地図を身近なものとして感じていただけるよう工夫しました。多くの方にご来場いただき、ひとあじ違う「測量の日」を体験していただけたらと思います。
測量・地図はあまりにも身近すぎて、その大切さを私たちは忘れがちです。測量・地図について私たちひとりひとりが関心を寄せ、考えていく必要があります。そんなところから「測量の日」がうまれました。
6月3日を「測量の日」としたのは、測量法が昭和24年6月3日に公布されたことに由来します。
基準点を大切にしよう。
基準点には「三角点」・「水準点」および「電子基準点」などがあり、すべての測量や地図作成の基礎・地震調査研究等に使用されます。

GPS測量風景

電子基準点
日本各地の地殻変動の監視や測量の基準等に利用するため、約20Km間隔で設置されており、全国で約1,200点あります。

三角点
見通しのよい山頂などに、約1.5Km間隔で設置されており、全国で約100,000点あります。
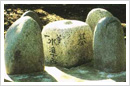
水準点
全国の主な国道や主要地方道に沿って約2Kmごとに設置されており、全国で約20,000点あります。

水準測量風景
測量は、生活の中でどのように役立っているの?
測量は、私たちの生活と密接に関わっています。
道路の設計・建設、都市の計画・開発や農地の整備などの公共事業を行うときは、基準点を使用して、正確な位置(緯度、経度、標高)を求める測量が必要です。
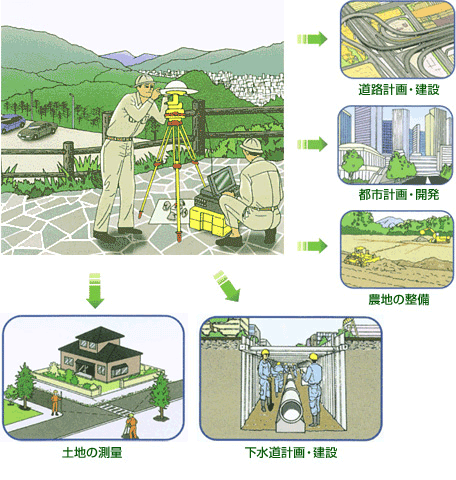
皆さんが土地を買って家を建てる際には、その土地を測量して位置や形、面積を調べ、設計図を作ったりすることが必要になります。
また、台所や浴室などから排出される生活雑排水が、下水道管を通って下水処理場へ流れて行くためには、方向や高さの正確な測量が必要です。
このように測量は、私たちの生活の様々な場面で、重要な役目を果たしています。
地図は、生活の中でどのように役立っているの?
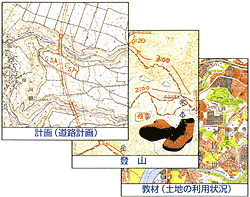
地図は生活、レジャー、科学などいろいろなところで利用され、また、活用されています。
地図は、各種調査・計画、教材として、また登山、レクリエーションの場面などに広く多方面にわたって利活用されています。
さらに、皆さまの街の道案内図、天気予報図など、生活に欠かせないものとなっています。
コンピュータで利用できる数値地図(デジタルマップ)は、GIS(地理情報システム)に不可欠な地図データです。
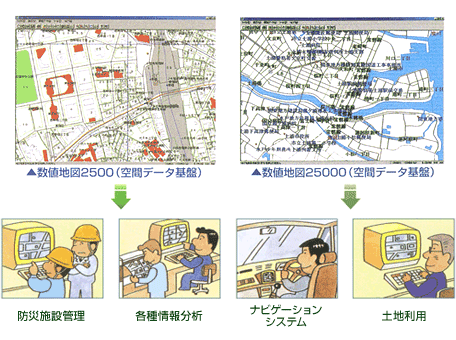
GIS(地理情報システム)は、様々な台帳・統計データを数値(デジタル)化された地図データの上に結びつけ、統合的に処理・管理・分析するコンピュータシステムです。GISを利用すると、カーナビゲーション、防災・災害分野や環境保全分野などへの利用ができ、高度情報化社会には不可欠なシステムです。
このように地図は、私たちの生活の様々な場面で、重要な役目を果たしています。