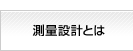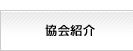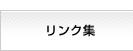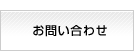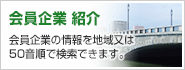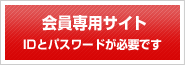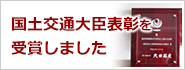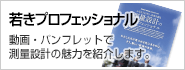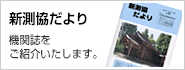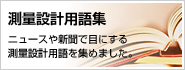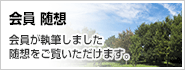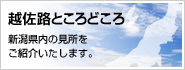心豊かな躍動するファッションと清流のまち 【五泉市】
五泉市は穀倉新潟平野の東部に位置し、東側に阿賀野川、中央に早出川、西側に能代川が流れる肥沃な地域です。また、東西には登山で賑わう菅名岳や護摩堂山などの山地、丘陵地が立地しており、新潟市まで約25km、新津市まで約10kmに位置しています。
市の成立ちは、昭和29年に1町3村が合併し市制施行、その後に隣接する3村の一部を編入して現在の五泉市に至っています。人口は約3万8千人、面積は98.8km2の五泉地域広域圏の中核都市です。
「五泉」の地名は、その昔「5つの泉が湧き出ていたから」や「5つの清水が流れていたから」など様々な説が言い伝えられています。
●繊維のまちの成り立ち
五泉といえば織物のまち、ニットのまちといわれるほど、まちを築き、まちとともに成長してきた繊維産業が農業とともに市の基幹産業となっています。
そのひとつ織物工業は、今から約250年前に、江戸時代に袴地「五泉平」(ごせんひら)を織り出したのが始まりです。絹織物に最高の環境といえる豊かな水資源と適度な湿気を利用し、全国で3本の指に入る自生地産地として、京都の丹後、滋賀の長浜とともに名を馳せました。最近では消費者の二一ズに応えて、洗えるシルク製品を開発するなど新たな活路を見出しています。
織物と並んで、戦後繊維産業革命ともいえるほど目覚しい発展を遂げたのがニット工業です。五泉ニットの成り立ちは、戦前からの絹織物、真綿加工、養蚕の時代から、戦後は真綿を撚ってチョッキを作るラップ業へと変わり、メリヤス横編み機技術導入と縫製技術があいまって五泉のニット産業が興隆し、日本一のニット産地となりました。

●産地の挑戦
めまぐるしく変化する流行を常に取り入れ、日本一の産地に成長した後も、技術を磨き品質の向上に努めてきました。しかしながら昨今の長引く不況による需要の低迷に加え、中国製に代表される安価な輸入品の急増により、現在は大変厳しい状況に置かれています。
平成6年には、中央アパレル依存の受託生産型産地からの転換を目指し、全国初の産地ブランド「GOSEN DREAM」を発表し、東京をはじめ各地でファッションショーや展示即売会などを行っています。
平成13年、市内の小学生からデザイン画を募集し、市内の各企業で製品に作り上げ、本人をモデルとしたファッションショー「キッズ・コレクション」を開催し、現在も大好評です。
平成14年度からは県の支援を受け、地場産業振興アクションプランを策定し、3ケ年事業で取組んでいます。五泉では、その優れた技術力を活かした商品企画提案力を特つ自立した産地を将来像としています。具体的にいうと五泉市のニット産業は、中央アパレルの受託生産が進むにつれ、商品の企画提案力を低下させていったものを、もう一度メーカー自身が主体的機能を回復させ、商品の企画力と提案力を持つ企業へ生まれ変わっていくことを目指しているものです。これは、ニットメーカー自らが商品の企画・提案できる先進のビジネスモデルヘの挑戦であり、同時に流通過程の簡略により商品価格の削減を進めていくものです。
このアクションプラン事業により、中央からデザイナーを五泉に招き、各メーカーに対しそれぞれ指導を行うものや、ITを利用し独自の流通システムを開発するなど、メーカーも徐々に自社の企画力を付け、商品を提案できるようになってきています。
また、この事業の一環で14年に東京の広尾にパイロットショップとして、「メーカーズニット 五つの泉」を開店しました。産地直営のこの店ではイタリアの高級な糸を使い、五泉の技術力を駆使して、高級セーターをリーズナブルな値段で販売Lていています。売れ行きは好調で、首都圏のマスコミにも取り上げられ、産地からの情報発信の拠点として期待されています。
![[GOSEN DREAM]発表会](https://www.shinsoku.org/wp-content/uploads/gosen_img02.jpg)
●新しい市場を求めて
次に市場開拓ですが、五泉市では産業の振興と活性化について、検討・協議し五泉市の行政運営に反映させるための組織「五泉市経済活性化戦略会議」を平成14年に立ち上げました。会議の主要テーマとしては、市の基幹産業であり、とりわけ市の経済にとって裾野の広いニット産業の振興と活性化を課題として取組んできました。
具体的に言うと、最近目まぐるしい発展を遂げている中国沿岸地区の上海周辺を市場としてとらえ、「五泉で製造したニット製品を売れないか、あるいは中国で作り、中国で売れないか」を検討しています。まさに発想の転換で、今までは日本の市場が中国製品に押されてきた状況を、逆に日木製品の市場として中国を捉えられないかといった発想が新しく、市内外から注目を集めました。14年7月に行った上海の市場視察には、新潟日報の記者の同行記事のシリーズ掲載や、テレビではNHK新潟の3夜連続の特集など「五泉の挑戦」といった切り□で取り上げられました。また、15年度も同様に市場の調査に市長をはじめとした視察団を送り、その可能性について検討を行っているところです。
●彩のまち、春花シリーズ
繊維産業が基幹産業であることから、「彩のまち」と例えられますが、近年では、水芭蕉、チューリップ、ぼたんなどの花々が咲き誇るまちとしても有名です。
3月下旬には市内東部の大蔵山のふもと郷屋地区の水芭蕉公園には、清楚な白い花だちが一足早く春の訪れを告げてくれます。
4月下旬になると、国の天然記念物に指定されている小山田の彼岸桜や粟島公園、桜橋などの桜並木は通る人全ての目をうばいます。また一面花のじゅうたんとなる巣本地区のチューリップも有名で、毎年150万本の色とりどりの花に囲まれてチューリップまつりが行われます。
5月には東公園内のぽたん園で115品種、5000株のぼたんが美しさを競い合うように大輪の花を咲かせ、人々の心を弾ませます。上旬に行われる「花木まつり」には、ぽたんの鉢植えを買い求める人や、あでやかなぽたんの姿を写真に収める人など、毎年多くの人が訪れます。

●清流のまち
五泉の名峰「菅名岳」には、樹齢300年余りのブナの原生林が生い繁り、春には新緑が、秋には紅葉が目に鮮やかな色を放ちます。そのふもとのいたるところから清水が湧き出ており、「胴腹清水」や「吉清水」が特に有名です。
「胴腹清水」は、その名のとおり菅名岳の中腹から清水が湧き出しています。そしてこの水は地酒づくりに利用されています。酒づくりには、寒の入りから9日目の水が最も適しているといわれ、毎年1月に行われる「寒九の水汲み」といわれる行事には、全国各地から数百名もの参加者が集まります。
「吉清水」は地元では「よしみず(吉水)」と呼ばれており、「良い水だ、良い水だ」と呼ばれていたのが変化して、今日の名前になってきたのだそうです。この水は、湧き出ている近くまで車で行けるため、連日市内外の人で賑わっています。
温泉も湧き出しているものの一つです。「咲花温泉」は、湯の花が咲いていたところから名付けられたといわれ、湯量豊富で素肌美人の湯としても有名です。また毎年7月の第4木曜目には水中花火大会が行われます。これは舟の上で点火した花火を水中に投げ込んで打ち上げるという全国でも珍しい花火です。

●天下一品「帛乙女」
水が豊富で肥沃な大地は、農業にも最適な条件といえます。稲作は、この豊富な水が命であり、五泉郷米と呼ばれる良質で味の良い米の生産は、農業の中心を担っています。
また、肥沃な大地からは優れた路地野菜が生み出され、県下有数の生産基地として有名です。なかでもさといもは「帛乙女」の名で知られ、きめ細やかな白肌と独特のぬめりで市場の評価も特に高く、消費者から好評を博しています。
ほかにもれんこんは地肌の白さと歯ざわりの良さが、キウイフルーツはビタミンの豊富さと糖度の高さが、ねぎは「やわ肌ねぎ」の名で知られ、やわらかさが身上です。
さらに当市はチューリップの球根やぼたんの苗木生産が行われており、球根生産では県下1、2位を争い、苗木生産では全国でも有数を誇っています。最近では付加価値の高い切花や鉢植え栽培も盛んに行われています。